大問1について
標準的なレベルの漢字の書き取り問題でした。しっかりと日々の漢字学習ができているかを確かめられる良問です。できれば全問正解したかったところですが、8問正解が合格といったところでしょうか。「4」「賞賛」の「賞」と「7」「余念」の「余」は、どの漢字にするか迷った人もいるのではないかと思います。「ショウサン」には「勝算」という同音異義語がありますが、「余念」はこれしかないので、「余念がない」というフレーズで暗記してしまってもよいでしょう。(四年もありますが、さすがにそれと迷うことはないと信じたい…)意味としては「熱中していて他のことは考えない」ということです。
基本的には、「賞賛」は「する・される」で使う、「勝算」は「ある・ない」で使われるものだということも覚えておくとよいでしょう。
小学生のお子さんは意外と「3」「最適」が苦手な印象です。間違ってしまった人は「最小」「最新」など「もっとも」を使った熟語を取り上げて、同じ種類のものだと覚えましょう。
大問2について
熟語の構成の問題ですが、これも標準的なレベルの問題です。「2」「読経」は知らない熟語だったかもしれませんが、「読書」と同じ構造だと分かれば解けたはずです。この中で一番難しいのは「4」の「明示」でしょう。「上が下を修飾するもの」は「高山(高い山)」のように下が名詞になっているものが多いですが、「明示」は「はっきりと示すこと」というように下の漢字が動詞の働きをする言葉なので、修飾被修飾の関係と気づけなかったかもしれません。「急行」なども同じパターンと覚えておきましょう。
大問3について
一・二と同様に、標準的なレベルの問題で、同音異義語・同訓異字が出ています。間違ってしまった人は要復習です。
大問4について
正解したかった基礎問題・・・問一、問二、問五のⅣ、問六
文章の前半部分こそ引用などもあり少々難しく感じられたかもしれないですが、知識や学びについての筆者の意見が述べられた標準レベルの論説文でした。前半部分を読むのに苦労してしまい余計な時間を費やしてしまった人は、説明的文章では何を読み取るべきなのかという指針がまだ確立されていないのかもしれないので、夏までにはしっかり身につけたいですね。「筆者の意見」に線引きができていない(注目できていない)人は要注意!
問一は易しめの四字熟語の意味の理解を問うものなので割愛します。問二の接続詞も易しいので、確実に得点したいところです。間違えた人は、接続詞の6種類(人によってグルーピングは違うと思いますので、習っている先生のグルーピング)を、まずはしっかり覚えなおしましょう。
問三は⑴も字数が限定されているのでそれほど難しくはないのですが、何が問われているのかの把握に苦戦した人もいるかもしれません。
問四の記述題は、やや難しかったです。問三、問五も同様なのですが、筆者の意見の部分に傍線が引かれている場合は、その理由を問われるケースが非常に多いです。「筆者の意見に傍線→理由を答えるのでは?」と、すぐに思えるようになっておきましょう。今回の問四は「欲する知」の内容を明らかにして、「どのようなことが~」と問われているので「言い換え問題だ!」と思ってしまったかもしれませんが、本質は理由の問題です。「問うことが身につ」き、「さまざまな情報に接することで」「情報を選別する力がついてくる」から「必要だと思っている」わけです。よって、問四は筆者の意見の根拠となる理由の部分を答える問題でした。
問五については、設問から筆者の意見の理由を問うものだとわかります。ここで必ず覚えておいてほしいことがあります。それは、リード文の穴埋め問題は、まず後ろから埋めることです。日本語ではふつう、結論が文の終わりにくるからです。逆に言うと、前半はいわばおまけのような内容になっていることが多々あります。おまけには何がくるか分かりません(もちろんパターンはありますが)しかし、結論は前に何がついても基本的に同じです。尊敬=リスペクトする気にならないのはなぜかと問われていますので、具体例の段落の次の段落にある「このことによって」に注目し、「著者とセットで知識を受け取る」を見つけましょう。字数が合わないので類義表現を探すと、「知識を与えてくれた人を意識」が前の段落に見つかります。これが、セオリー通りの解き方でしょう。
ここで、「うーん、イマイチ納得できないなあ」という人や、「答えを言われるとそれはそうなんだけど、この見つけ方はちょっと難しすぎるなあ」という方は、他にもアプローチの仕方があります。ここで別の解法を解説してしまうと、混乱してしまう可能性もありますので、参考にされたい方は別途お問い合わせください。
大問4について
正解したかった基礎問題・・・問一、問二、問三,問四の⑴のⅢ・⑵
問一は場面分けの問題でした。「時・場所(・人物)」が変わったところで場面を分けてもらいたいのですが、いくつも意識できないという人は、まず時間の変化に注目して読む習慣をつけてください。
問二の⑵は、「言動の理由」の問題だとすぐに気づけましたか?「できごと→心情→言動」を用いた解法がまだしっかり理解できておらず、なんとなくで解いてしまっている人は、仮に正解していたとしても要注意です。どのように解いたのかをしっかり説明できるか、ご家庭で確認してみてください。
問三は様子が問われているが、心情が問われていると考えてください。そして、問二の⑵と同様に「できごと→心情→言動」を用いて解けたかを確認するとよいでしょう。また、「ア」を選んでしまった人は要注意です。質問をしっかり理解できていない、または、その場面で起きたできごとを読み取れていない可能性があります。
問四の⑵は「きまりが悪い」という言葉の意味がわかっていれば解けた問題です。
問五、六が全く分からなかったという人は、この場面で起きていることや、行動・発言の意図をしっかり復習し、この機会に学んでおきましょう。
問八の記述は、「55字も書くことがない」と困ってしまった人がいるのではないでしょうか。そういう人は、「心情の変化を考える」ということができていなかった可能性が高いです。
より詳しい解説や、疑問点の解決など、直接のご指導をご希望の方は、お気軽にお問い合わせフォームかメール、LINEにてお問い合わせください。

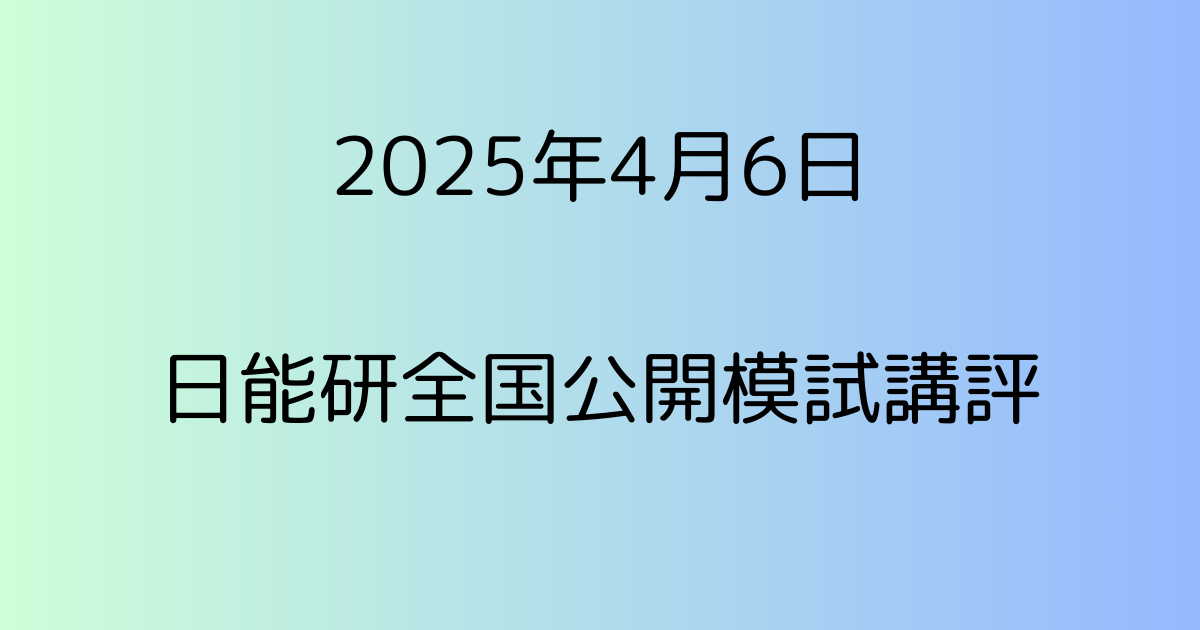
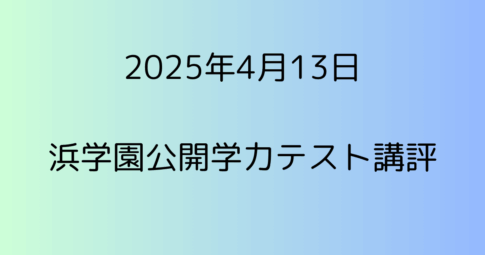


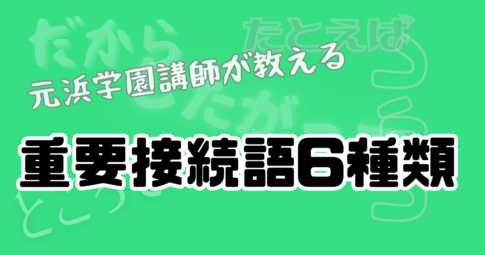
コメントを残す